埼玉県の実家へ帰郷
コロナの影響もあり、私は約4年ぶりに実家のある埼玉県草加市に帰ってきた。
その時、学生時代の友人と久々に話す機会があった。
友人は現在結婚をしていて、旦那さんと4歳の子ども1人がいる。
彼女は実家を改装して、二世帯でずーっと地元埼玉に住んでいる。
というのも、彼女の実家の家業は保育園で、彼女も現役で手伝っているからだ。
私も以前保育士だったのでよーく分かるが、4歳の子どもを育てながら、保育園で保育士の仕事をしているなんて、なかなかハードだなと思った。
久しぶりだったので、最近の保育園の様子聞いてみた。
保育士を取り巻く現状

友人のところは最近認可保育園の申請が通って、国からの補助金などが充実したことで前よりも仕事にゆとりが出てきたとのこと。
シフト制にして、さまざまな仕事を分業して行っているらしい。
今は新しいスタッフの採用に力を入れいているんだそうだ。
そのために、連絡帳をアプリを導入したり、運動会やお遊戯会などの大規模なイベントを辞めたりして、保育士の働きやすさに重点を置いている。
彼女の話を聞いていて、私の働いていたころの保育士のイメージと随分ズレがあった。
すぐに保育士について調べてみると、数年前から厚生労働省が保育士の働き方に関して改善政策を推進している。
特に興味深かったのが、「潜在保育士」と呼ばれる資格を持っていても保育の仕事に従事していない私のような人が、全国で約95万人(平成30年時点)もいることだった。
(参照元:厚生労働省 保育士の現状と主な取組)
潜在保育士を対象とした雇用促進政策
埼玉県では、人材不足解消のために潜在保育士を対象に引っ越し費用や研修費用に使える「就職準備金貸付」、自身の子供の保育料を対象とした「保育所復帰支援貸付」という補助金制度があるんだそう。
保育士を目指す学生向けにも補助金制度を用意されているみたいだ。
保育士だけを対象にした補助金があるなんて、やはり埼玉県も労働環境改善に相当力を入れているようだ。
「持ち帰りゼロ」って?
埼玉の求人をチェックしていると「持ち帰りゼロ」「持ち帰り仕事なし」というキーワードが目立っていた。
私からすると「持ち帰りゼロ」ってなに?って感じ。
就業時間は子どもと向き合うことだけ精一杯なので、休日には
- 保育経過記録
- クラスのおたより
- 行事用の制作物作成
- 週報や月案の指導計画
などなど、やることをたくさん抱えていた。だから、家に持ち帰って仕事をするのは保育士業界では当たり前でしたからね。
こうしたサービス残業が常態化しているのは良くないこと。
保育士を取り巻く労働環境が当たり前になっていたことが「潜在保育士」を増やしてしまった原因のひとつだったのだ。
私が保育士を辞めた理由

私が保育士を辞めた理由は、いわゆる人間関係。
埼玉県の公立の保育園に努めて3が年経ったころ、尊敬していた園長に変わってきた人が、あまりにも子どもと向き合った保育をしていなかったからだ。
私が保育士になったのは子どもが大好きだからで、クレームにおびえてやってはいけないことばかりをルール化し押し付けてくる、新しい園長と全く馬が合わなかったからです。
話合いや言い合いも下のですが、どこまで行っても平行線のままで、ほとほと疲れ切ってしまって保育の仕事自体から身を引きたくなってしましました。
埼玉県の保育士求人
友人の彼女の保育園の話や、最近の埼玉県の保育士雇用促進政策の内容が分かって、ふつふつと地元埼玉で保育士として復帰してみたいと思うようになった。
確かに、保育施設や働き方、さまざまな条件を絞って探すことができる保育士求人サイトはとても便利だ。
サイトによって、期間限定だが、保育士の収入を3か月間もの間なんと、5万円もアップする求人もある。
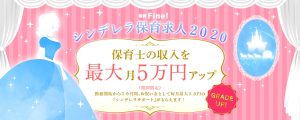
今だったら、地元埼玉で保育士として復活できそうな気がしてきた。
参考:埼玉県の保育士求人、幼稚園教諭の転職なら【保育Fine!】
保育士はつらいよ 2021
ふるさとに戻ると、新たな人生が動きだしたように感じた。
こうして、さまざまな保育士への支援が行われたり、働く環境も改善されてきているが、それでも、保育士にはつらいことや、苦しいことはきっと待ち構えているだろう。
けれど、私のよに、「ずっと子どもと向き合って働ける場所」が見つけやすくなったのも、こうした動きが出てきた、今だからだとも思う。
難関の保育士試験を突破し、夢と希望を持って保育士になった保育士たちが、潜在保育士になってしまう現状は、とても悲しいことで、日本の社会にとって良くないことだ。
現役で戦って働き方改革をして来た人もいるだろう。
また、私たちのよに潜在保育士となったサイレント・マジョリティが、戦ってきたからこそ、すこしづづ保育業界も変わってきたのだ。
これから保育士の仕事はもっとよくなって行くように感じる。
保育士としての本分や役割への認識も変わってゆくことだろう。



